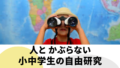夏の風習の「お盆」」、そして 春と秋の年に二回ある「お彼岸」の一週間は、ご先祖様を供養する大切な期間です。この記事では、「お彼岸」をはじめとした 普段からのお墓参りにも必要な準備物や具体的な方法をわかりやすく説明します。
お墓参りで必要な準備

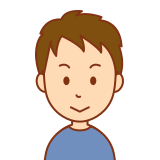
お彼岸などで お墓参りに行く時には
次のものを準備しましょう
・お線香
・ろうそく
・ライターまたはマッチ
・お花
・お供え物(お菓子や果物、故人が好きだった物など)
・半紙(お供え物を置くため)
・掃除道具(ほうき、ちりとり、タオル、スポンジなど)
他にも 墓石の彫刻部分を掃除するための歯ブラシもあると便利です。また、雑草取りや草刈りの道具、ハサミやペットボトルなどの容器に入れた水も準備しましょう。
特に 水場がない場合や、バケツや手桶、柄杓が必要な場合には、持参が必要です。
お墓の状況によって準備物が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
お墓参りでの作法

時間と服装
お墓参りする時間に関しては、霊園や墓地に特別な規則がない限り、決まった時間はありません。
ただし、お彼岸は故人やご先祖様を偲ぶ大切な日です。他の用事よりも優先して、できるだけ午前中にお参りするのが良いでしょう。
服装についても特に決まったものはありませんが、きちんとした服装が望ましいです。掃除をすることを考えると、動きやすい普段着の方が適している場合もあります。
また、お数珠を持参することが望ましいですが、最も重要なのは故人を思う気持ちです。形式にとらわれず、心を込めてお参りすることが大切です。
お墓の掃除方法
お墓参りは、まず墓石と墓地のお掃除から始めます。お掃除の前には、お墓に向かって
一礼し、感謝の気持ちを伝えましょう。
枯れた花や残ったろうそく、線香の燃えかすを取り除き、水鉢や花立てなど特に汚れやすい部分を念入りにきれいにします。取り外せる部品は取り外して洗うと良いでしょう。
墓石はタオルやスポンジで丁寧に拭き掃除します。基本的には水を使い、家庭用洗剤は
シミの原因になるので避けます。
彫刻部分の汚れは歯ブラシを使って落としましょう。
墓石だけでなく、周りの掃除も忘れずに行いましょう。
お参りの手順
お墓がきれいになったら、水、線香、お花、故人の好きだったものなどをお供えし、心を込めて合掌礼拝します。
ろうそくや線香の火を消す際には、息をかけず手であおいで消します。仏様に息を吹きかけるのは失礼とされているので注意しましょう。
故人が好きだったお酒を供える場合も、墓石に直接掛けるとシミの原因になるため、周りに掛けるようにしましょう。
また、お墓に水を掛けることについては意見が分かれますが、お参りする人の気持ちに従うと良いでしょう。
お花を供える際には、先にお参りした方のお花がまだきれいな場合、傷んだものを抜いて持参したお花を追加します。風で飛ばされないよう短めにして挿します。お供え物は半紙などを敷いてから供えます。
お墓参りが終わったら
お参りが終わったら、お供え物は持ち帰ります。放置するとカラスなどに荒らされることがあるからです。
また、掃除で出たゴミも持ち帰りましょう。墓地にゴミ箱がある場合には、分別ルールに従います。
お彼岸の供え物について
お供え物には、故人が好きだった食べ物やお菓子、果物が一般的ですが、最近では和菓子やフルーツが特に人気です。
また、地域によっては特産品を供えることもあります。故人の好みに合わせて選ぶと良いでしょう。
こうした中、環境保護の観点から、プラスチック製のお供え物や花を避ける動きも見られます。自然素材を使った供え物やエコフレンドリーなアイテムを選ぶことで、環境にも配慮したお墓参りができます。
- 季節の花
- ぼたもちやおはぎ
- 彼岸団子
- 季節の果物
- 故人が好きだった食べ物
- 精進料理
- お線香
- ろうそく
- お茶
- お水
お彼岸の期間
お彼岸の期間は、春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)として、その前後3日間、合計7日間です。
お盆とは違って「お彼岸休み」というのは存在しませんが、シルバーウイークといわれる 9月の連休に重なることも多い傾向です。
2024年 春と秋のお彼岸
春分の日は 3月20日(水・祝)なので、 春のお彼岸は 3月17日(日)から3月23日(土)までです。
また、秋のお彼岸は、秋分の日が 9月22日(日)なので、 秋のお彼岸の期間は、9月19日(木)から9月25日(水)までとなります。
デジタル化で普及したサービス

ここ数年間で、遠方に住む家族が多いため、オンラインでの墓参りサービスも普及してきました。これは、現地の業者が代わりにお墓参りを行い、その様子を写真やビデオで報告するサービスです。
また、最近 話題になっている「人生の仕舞い方」終活においても、自分流に人生を閉じ自分流のお葬式を希望する等、既成概念から脱却しつつある昨今、葬儀やお墓の概念も変わってきています。
昔からの習わしや決まり事に縛られず、各々が決めることといった傾向は、お墓参りのあり方にも新たな選択肢を増やしたといえるでしょう。そのひとつが「ネット墓参り」です。
忙しい現代社会において、このようなサービスを利用することで、離れていても 先祖を敬う気持ちを表すことができます。
まとめ
お彼岸などのお墓参りは、私たちが先祖に感謝し、その恩恵を改めて感じる大切な行為です。
準備物を揃え、正しい方法でお墓を掃除し、心を込めてお参りすることで、故人との絆を深めることができます。
お参りをする時期・持ち物・服装などにおいて、絶対的なルールはありません。
しかし、一般的なお参りの作法やマナーは存在します。 お墓参りは、ご先祖様の冥福をお祈りし、清らかな気持ちで行いたいものです。
時代に合わせた供養の方法を選ぶことで、より充実したお彼岸を過ごすことができるでしょう。